





2025.3.4
道路際の冬期湛水田の横を走行中、赤い大きなカモが1羽浮かんでるのが見えた。すぐに車を止めて双眼鏡で確認すると、予想どおりのカモだった。アカツクシガモ。図鑑でしか見たことのない赤い大型のカモ。カルガモとマガンのちょうど中間程度の大きさ。
モンゴルから中央アジアにかけてユーラシア大陸中緯度の広いエリアを繁殖地に持ち、冬はまっすぐ南に下がって越冬することが、図鑑の分布図に示されている。日本への迷行飛来は西日本を中心に稀。そんなカモが目の前にいるのである。
あいにくの風雨で、証拠写真程度しか残せなかったが、飛来直後と思われ、警戒心が非常に強かった。近くを大型ダンプが通るたびに飛び立ち、しばらくすると同じ湛水田に戻って来るのを繰り返した。
















2025.3.5
翌日は早朝より、記録写真をしっかり撮ろうと飛来地を訪ねた。次第に警戒心も弱まって、徒歩で水路の中からレンズを構えて撮影することも許してくれた。
首の付け根に明瞭な黒いリングがあり、成鳥オスであることがわかる。英名はRuddy Shelduck。Shelduckはツクシガモ族の英名で、赤いツクシガモでアカツクシガモである。高校生の頃、生物部の仲間がアカツクシガモの名を口にしているのを聞き、「赤尽し鴨」とばかり思っていた。





2025.3.10
初認から6日目、アカツクシガモはなお同じ田にいたが、湛水田の水が落とされ、渡去のタイミングが近づいてきた。仲間の観察によれば、ここからすぐ北の海に浮かぶ様子もみられた。
2025.3.12
同場所から姿を消した本個体が、そこから北東2.5kmの円山川下流ワンドにいるのを仲間が確認したのが、終認となった。3月4日の初認から8日間の、アカツクシガモの豊岡市での逗留記録となった。
アカツクシガモの目撃情報は東日本にかけても稀にあり、ネット情報によれば、飼育個体の野外への逃げ出し、いわゆる「カゴ抜け」が多いとのことであった。今回の飛来個体も、ひょっとしたらカゴ抜け可能性も考えられるが、当地の西の米子市や出雲市でも、ときどき野生個体の飛来確認があることで、野生個体としてよいだろう。
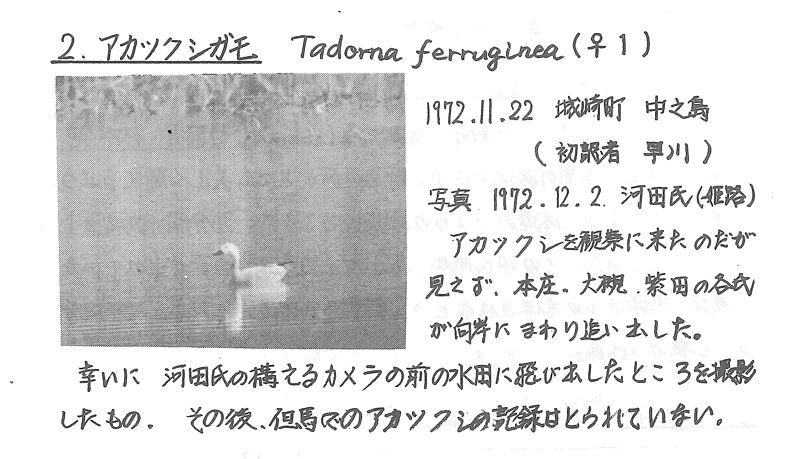
「但馬野鳥の会」の会誌”Lapwing” Vol1(1982.5.10 発行)の掲載記録を上記に引用する。
これが豊岡市での唯一の飛来記録として残っているものであり、今回の記録は1972年以来の53年ぶりということになろう。1972年の飛来個体はメスとされており、今回のオス個体の飛来は初である。もっとも、飛来していても目撃記録がなければ、来ていないのと同じことではあるが。
さらに調べると、豊岡市の東隣の久美浜湾では、1986年12月13日に雌雄ペアでの飛来が鳥仲間のT氏により目撃されており、写真も撮られている。My Fieldという範囲でみれば、1986年以来39年ぶりということになろう。
当地への飛来時、冬型の気圧配置で寒気が流れ込んでおり、大陸の北帰行個体が気流に流されて当地まで流されてきたのだろう。当地から去ったあと、このアカツクシガモはどこかで再認される可能性がある。次の中継地でもまた、野鳥ファンの注目の的になるのだろう。当地への再飛来は、もう私が生きている間には無いのかもしれない。あるいは、気候変動の影響がアカツクシガモの渡りのルートを東寄りに変えたのかもしれない。いろんな可能性を考えながら、いつかの再会を待ちたい。
撮影:D7500+VR300mmF4.0
